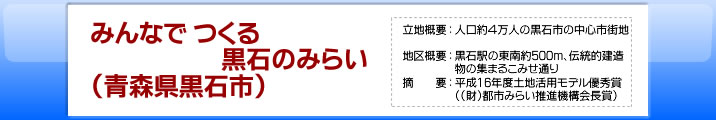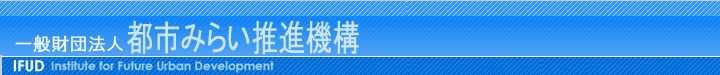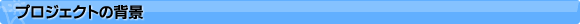 |
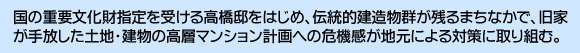 |
| �E |
1980�N�㔼�ɁA���݂��ʂ�ɖʂ������Ƃ�������y�n�E�����Ւn�ɁA�f�B�x���b�p�[�̃}���V�����v�悪����������A�i�b�W�҂Ȃǒn���L�u�Ɋ�@�������܂�B |
| �E |
1989�N�ɗp�n�����A1990�N����u���݂��̉�v��ݗ����Ė{�i�I�ɂ܂��Â���ɏ��o���A�`���I�Ȃ܂��Ȃ݂������n��̊������Ɏ��g�B |
|
|
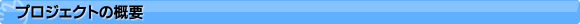 |
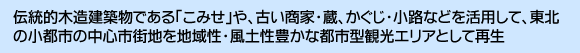 |
| �E |
�n���L�u�ł���i�b�����o�[����̂Q�O�l�̌l�����ɂ���ēy�n�E�������擾���A�}���V�������ݗ\��n�����A�P�X�X�O�N�Ɂu���݂��̉�v��ݗ����A�܂��Â���Ɏ��g�ށB |
| �E |
���݂��̉�W�������L����Ёu���Ɂv�E�u���݂��w�v��ݗ����A���Ƃ̌����Ȃǂ����p�����ό��E�𗬂̏�u���݂��w�v���P�X�X�V�N�ɃI�[�v�����A�������X�X�̗��n�i�������j�𗘗p�����L�ꐮ�����V�H������i�߂�B |
| �E |
�P�X�X�W�N�Ɂu���Ύs���S�s�X�n��������{�v��v���쐬���A�Q�O�O�O�N�ɂ͂i�b�����o�[����̂Q�O�l�Ə��H��c���N���𒆐S�Ƃ���P�P�U���̊���ɂ���Ăs�l�n�u�Ìy���݂�������Ёv��ݗ��A�u���݂��w�v�̉^�c�������p�����������_�{�݁u�Ìy�����݂��w�v�Ƃ��ĊJ�Ƃ����B |
| �E |
�Ìy���݂�������Ђ����S�ƂȂ�A�����̍��Ύs�Z���������c�Ƃ��āu���݂��v�ۑS�E���p�̎��g�݂������A�����P�V�N�S���ɂ́A���̏d�v�`���������Q�ۑ��n��i�d�`���n��j�̎w��Ɍ��т��Ă���B |
| �E |
�u���݂��w�v�͂�����ό��y�Y���𒆐S�Ƃ���X�܂Ƌx�e���ŁA�Ìy�O�����̃��C�u���͂��ߏ�M�I�ȋ@�\���S���Ă���B |
| �E |
�Q�O�O�Q�N�ɂ́u���ړI�z�[�����݂���v�A�u�C�x���g�L�ꂶ���L��v����������ȂǁA�܂��Â���̔��W�I�W�J�ɓw�߂Ă���B |
|
|
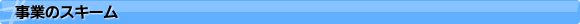 |
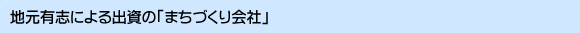 |
| |
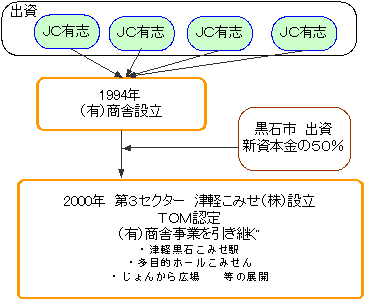 |
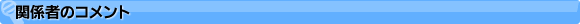 |
|
|
 |
| ���Ìy�����݂��w�@�O�� |
|
 |
| ���Ìy�����݂��w�@�X�� |
|
 |
| �����݂���Ƃ����L�� |
|
 |
| ���������݂���@�W���Y���C�u |
|
|
 |
���c�@�l�@�s�s�݂炢���i�@�\
��112-0013�@ �����s�����批�H2-2-2 �A�x�j���[���H�r��3F
TEL.03-5976-5860�@FAX.03-5976-5858
���[���͂����� |
|
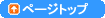 |